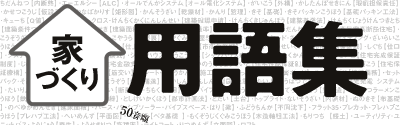
パンフレットの中で、営業マンの話の中で、建築現場担当者との打ち合わせの中で。。
家づくりを進めていくと、日頃はなじみのない専門用語を見たり聞いたりすることが多くなってきます。
そんな言葉の中から、主なものを集めたのがこの用語集。
もし、わかりにくい言葉、気になる言葉に出会ったら、ここでチェックしてみてください。
あ行
アールエムぞう【RM造】
ラーメン構造の略。ラーメン(rahmen)とはドイツ語で枠のこと。柱と梁の接合点をしっかりと固定(剛接)した枠組み。筋交いがないので、大きな開口部をとったり、大空間を確保したりできるのがメリット。
アールシーぞう【RC造】
鉄筋コンクリート(reinforced concrete)造の略。コンクリートを鉄筋で補強した構造材を用いた構造で、主に圧縮に強いが引っ張りに弱いコンクリートに、引っ張りに強い鉄筋を組み合わせている。耐久性・耐火性・耐震性のある建物をつくり出す。
アクティブソーラー
住まいの空調・給湯機器に、太陽電池などの設備や機械を使用して日射のエネルギーを利用すること。太陽光発電システムなどがその代表的な例。これと対照の方式が「パッシブソーラー」。
アプローチ
道路から門を経て玄関にいたるまでの導入路、およびその周辺。
アンカーボルト
土台が基礎からずれたり、外れたりするのを防ぐため、コンクリート基礎に柱、壁などを緊結させる埋めこみ式のボルト。「基礎ボルト」ともいう。
いぬばしり【犬走り】
建物の周りに40 ~60 位の幅でコンクリートやレンガ敷き、砂利敷きした部分。雨水によって基礎部分が濡れたり、汚れが建物に跳ね返ったりすることを防ぐ。
ウォークインクローゼット
人が歩いて入れる収納スペース(納戸)のこと。ハンガーパイプや棚板などが当初から設置されていることが一般的。
うちだんねつ【内断熱】
建物の内側、すなわち天井や壁、床下、柱と柱の間などの、躯体内の隙間に断熱材を充填すること。室内を包み込むように家の内側から断熱する。正しく施工しないと、内部結露が起きる恐れがある。
エーエルシー【ALC】
発泡剤で軽くした軽量気泡コンクリート。板状にしたものはALC板またはALCパネルという。軽量で断熱性、耐火性が高く、施工、加工が容易。壁・床・屋根材に利用される。
オールでんかシステム【オール電化システム】
冷暖房設備や給湯、調理設備など、住宅内の熱源をすべて電気としたシステム。火災の心配が少なくなり、室内の空気も汚れないことなどが特徴。
か行
がいこう【外構】
住宅の敷地内における外まわりの総称。塀や生垣、門扉、車庫、庭などのこと。
かしたんぽせきにん【瑕疵担保責任】
売買などの有償契約で、その目的物に通常の注意では発見できない欠陥がある場合に、売り主(請負者)などが買主などの権利者に対して負うべき賠償責任のこと。権利者には損害賠償権や、場合によっては契約解除権が認められる。なお、請負契約で規定されている瑕疵は施工上のものであり、設計上のものは含まない。
かせつこうじ【仮設工事】
建物本体を完成させるための一時的な設備工事。工事完了後は撤去される。足場などの工事がこれに含まれる。
かなばかりず【矩計図】
建物の各部分の標準的な高さを示す垂直断面図。縮尺は20分の1、30分の1が多く、切断された位置での、基礎の深さや屋根の勾配、天井や窓などの高さが示される。
かんそうざい【乾燥材】
含水率19%以下の、十分に乾燥させた木材。住宅に使用する木材は、水分が多すぎると、後で反りや曲がりなどの原因になることがあるので、乾燥した材料を用いる。自然乾燥と人工乾燥によるものがある。
かんり【監理】
工事施工中の建物が、正確に図面通りになっているかどうかを確認する作業。建築士が行う。設計者側の立場からの監督業務であり、施工業者の現場監督業務である「施工管理」とは異なる。
きそ【基礎】
建築物を支え、建築物の荷重を地盤に伝える下部構造のこと。独立基礎、布基礎、ベタ基礎などがあり、工法として直接基礎、くい基礎、ピア基礎などがある。
きそパッキンこうほう【基礎パッキン工法】
基礎と土台の間に専用のパッキン材を挟み込むことにより、湿気のこもりやすい床下の換気を滞りなく行う工法。通常の床下換気口の1・5~2倍の換気能力が得られる。
キューち【Q値】
正確には総熱損失係数という。建物の内側から外へ逃げる熱の割合を表す数値で、住宅の総合的な断熱性能を示す。数値が小さいほど断熱性能は高く、省エネルギー効果が大きいと考えられる。
くたい【躯体】
建物の骨組み・構造体。建物の強度にかかわる基礎、柱、梁、壁面、床などを指す。
クロス
壁紙の総称。紙製、布製、樹脂化粧、繊維製など各種あるが、紙というと安っぽいので、布地のクロスで表現している。塩化ビニールクロスが主流で、壁と天井仕上げ材として使われる。
けんちくかくにんしんせい【建築確認申請】
建築などの計画内容が法令の規定に適合することについて、都道府県や特別市町村に置かれる建築主事の確認を得るために、着工前に行う申請。
けんちくきじゅんほう【建築基準法】
建築物の敷地、構造、設備及び用途に関して最低の基準を定めた法律。地震や火災などから生命や財産を守るために建築の構造などに制限を加え、都市の生活環境の保護と都市機能の更新を図るために、用途への制限を加えている。
けんちくじょうけんつきとち【建築条件つき土地】
土地の売買契約後、3ヵ月以内に建築請負契約を結ばないと無効になるという条件のもとで販売される土地。住宅メーカーや工務店などが分譲し、実際の建築請負契約先もそこになることが多い。3ヵ月以内に建築請負契約を結ばなかった場合、土地に関する契約も白紙に戻すことになり、支払った代金は手付金を含めて全額返してもらえる。
けんちくめんせき【建築面積】
建物を上から見た時の外形による水平投影面積。建坪(たてつぼ)ともいう。一般的には、1階の床面積となることがほとんど。
けんぺいりつ【建ぺい率】
敷地面積に対して建築面積が占める割合。用途地域に応じて建ぺい率の限度が決められている。
こうきみつこうだんねつじゅうたく【高気密高断熱住宅】
家全体の断熱効果を高めるため、高性能の断熱工事を行い、かつ隙間から熱が逃げないように気密性を高くした住宅のこと。冷暖房効率が良い、表面結露を防ぐ、部屋間の温度差が少ないなどのメリットがあるが、換気と通風に対しての留意が必要。
コーキング
水密、気密を目的として目地や隙間などを埋めること。シーリングともいう。合成樹脂または合成ゴム製のペースト状の材料で、外装材の継ぎ目部分や窓枠周り、ひび割れ部分などに充填する。
こうぞうざい【構造材】
建物の荷重や地震や風圧などの衝撃に対し、それを支えるための主要な部材。木造軸組み構造であれば、土台、大引、床梁、床桁、通柱、管柱、隅柱、小屋梁、小屋束、母屋、垂木、棟木など。
ごうはん【合板】
厚さ5 以下の木材の単板を奇数枚、繊維方向が直角になるように交互に重ねて張り合わせた板。強度もあり木材の欠点である不均一性が改良される。通称ベニヤ板。構造用の面材や各部の下地材、仕上げ材として広く使用される。
こやうら【小屋裏】
屋根の下と天井の上の間にある空間。天井を張らずにロフトや収納として空間の利用法がある。熱や湿気がこもりやすいので、換気、断熱に留意する必要がある。
こやぐみ【小屋組】
屋根の荷重を柱や壁に伝える骨組のこと。和小屋と洋小屋がある。
コンパネ
コンクリートパネルの略。コンクリートを流し込む際の型枠を構成する耐水合板のこと。床仕上げの下地材によく使われる。
さ行
サービスヤード
台所に通じる屋外の家事作業スペース。洗濯機を置いたり、物干し場やゴミ置きのためのスペースとして使う。
さいこう【採光】
室内に自然光を採り入れること。建築基準法では建物の用途ごとに、床面積に対して必要な採光のための開口部の最小面積を定めている。
サイディング
外壁に張って使用する外壁仕上げ材の総称。色彩・柄が豊富。代表的なものに石綿セメント板や金属板などをパネル状に成型したものがあり、耐水・耐候性、防火性などに優れている。
ざいらいこうほう 【在来工法】
木造軸組工法とも呼ばれ、柱(垂直材)と梁(水平材)で構造体を構成する日本の伝統的な建築工法。ただし、これだけでは横風や地震に弱いため、柱と柱の間に筋交い(すじかい)という部材を斜めに用いる。
サニタリー
トイレや浴室、洗面室など、衛生のための水回り設備がある空間の総称。キッチンは含まない。
しあげざい【仕上げ材】
建物の内外装に使用する、直接目に触れる部分の表面材料。サイディングやタイルなどの外装材も含む。
しがいかくいき【市街化区域】
都市計画区域の無秩序な市街化を防止し、計画的に市街化を図るために都市計画法で定められた区域のこと。すでに市街地を形成している区域か、10年の間に市街化を図るべきと判断された区域かのいずれか。
しがいかちょうせいくいき【市街化調整区域】
都市計画区域の中で、市街化を抑制する意味を持った区域のこと。山林や農地などが中心で、基本的には住居も含め建物は許可なく建てられない。
しぐち【仕口】
2つ以上の部材をある角度をもって組み合わせて使用するとき、材どうしの接合部をいう。仕口は軸組全体の強度を大きく左右する。
システムキッチン
キッチンでの作業に必要な流し台、調理台、レンジ、調理道具・食品・食器・調味料の収納などが、キッチンの空間に合わせて自由に組み合わせて選べるキッチン設備のこと。
しぜんかんき【自然換気】
機械を使わずに換気する方法。風力換気と重力換気がある。風力換気とは、風圧による換気のことで、重力換気とは室内外の温度差による空気の重さの違いから、煙突効果が起こり行われるもの。
シックハウスしょうこうぐん【シックハウス症候群】
新築直後の家で、合板や接着剤、壁材、塗料などに含まれる化学物質が原因で起こる体調異常のこと。建築の計画段階から、使用される建材や素材を十分に吟味することが望ましい。
じゅうたくかんせいほしょうせいど【住宅完成保証制度】
全国の住宅建設業者を対象とした制度で、工事を依頼している建設会社がこの制度に加盟していれば、万が一建設会社が倒産しても、工事の続行が保証される。倒産した建設会社に代わって別の業者が工事を請け負い、その工事費用は保険などでまかなわれるしくみ。
じゅうたくきんゆうしえんきこう【住宅金融支援機構】
2007年4月、以前の住宅金融公庫の業務を継承する形で発足した独立行政法人。従来のように住宅ローンを直接融資する業務は行わず、民間金融機関による長期固定金利型住宅ローンを支援する証券化支援業務が主な業務。民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する長期固定金利住宅ローン「フラット35」を利用した場合、その返済先は住宅金融支援機構となる。
じゅうたくせいのうほしょうせいど【住宅性能保証制度】
住宅保証機構が実施している、住宅の品質と性能を保証する制度。同機構に登録している業者が建てた新築一戸建て住宅などについて、基礎、床、屋根など構造上重要な部分について最長10年、その他の部分については1~2年の間、品質と性能が保証される。
じゅうたくほしょうきこう【住宅保証機構】
住宅性能の向上、消費者の保護及び住宅建設業者等の育成を図り、それにより国民の居住水準の確保と住宅の供給に携わる者の健全な発展に寄与することを目的としている財団法人。
しようしょ【仕様書】
工事内容で、図面では表現できない事項を文章や数値で表示したもの。
すじかい【筋交い】
建物の構造を強固にするために、骨組の中に斜めにいれる部材。引張り力に耐える引張筋交いと、圧縮力に耐える圧縮筋交いとがある。
スレート
内外装の材料。天然のスレートと人工のものがある。天然スレートは粘板岩などを薄板に加工。独特の質感があるが高価。人工のスレートはセメントに石綿を混ぜて高圧プレスしたもの。主に屋根葺きの材料となる。
せこうかんり【施工管理】
工事現場での作業が円滑に進むよう、工事の計画や段取りをしたり、工事にあたる人員を指揮・制御するといった、着工から竣工まで施工業者が行う一連の管理業務のこと。設計者側からの監督業務である「監理」とは異なる。
せっこうボード【石膏ボード】
焼石膏を主原料とした芯材に、両面を厚紙で覆って平らな板状にしたもの。プラスターボードともいう。防火性、遮音性、施工性などに優れ、主に壁や天井の内装の下地材として使用される不燃材料。
せつどうぎむ【接道義務】
建築基準法上、都市計画区域内に建物を建てようとする敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上に接していなければならない。接道が2m以下の場合は、その土地に建物を建てることはできない。
セットバック
前面道路の幅員が4m未満の場合に、道路の中心から2m後退したところまでを道路として負担すること。セットバック部分は敷地面積に換算されないため、建ぺい率・容積率の計算から除外される。
そとだんねつ【外断熱】
基礎から壁、屋根まで建物全体を外側から包むように断熱する方法。内断熱より隙間はできにくくなるが、断熱面積が大きくなるため多少割高になる。
た行
たいかこうぞう【耐火構造】
建築物の主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)が必要な耐火性能をもつ建築物の構造を呼ぶ。RC造・鉄骨造は耐火構造となりうるが木造はそれになることはできない。
たいしん・めんしん【耐震・免震】
耐震は地震に対して建物を頑丈にして耐える考え方。一方、免震は地震のエネルギーを建物に伝達させないようにする考え方をする。耐震では建物が倒壊しなかったとしても揺れは伝わってしまうため、屋内の家具が転倒したり、水道・ガス管が破損したりする可能性が高い。そのため、近年では揺れが建物に伝わりにくくなる免震の研究がすすんでいる。
たいようこうはつでんしすてむ【太陽光発電システム】
屋根に設置した太陽電池パネルで太陽光を集めて発電させた電気を、家庭で使用できるようにしたシステム。排出物による環境汚染がなく燃料を消費しない。最近では、屋根材と一体になった発電装置もある。
たいりょくへき【耐力壁】
建物の主体構造として、上下および左右からの加重や外力に対して有効に働く壁。木造軸組の場合は筋交い入りの壁がこれにあたる。
だんねつざい【断熱材】
ロックウール(岩綿)、グラスウール(硝子綿)、スタイロフォームなどの空気層を多く含んだ材料のこと。外壁や屋根の下地に使用し、内外の熱の出入りを防ぐ。
ちもく【地目】
土地の利用状況を示す登記簿上の分類。住宅を新築するのに適さない地目の土地に建築する場合は、地目変更手続きが必要。
ツーバイフォーこうほう【2×4工法】
住宅の構造材に断面サイズが2×4インチの製材が使われる工法。「枠組壁工法」で躯体をつくる。
てっこつぞう【鉄骨造】
鋼鉄でつくられた鉄骨部材を組み立てて構成される工法。RC造に比べて建物を軽くつくることができる。燃えにくくて強度も高い。重量鉄骨造と軽量鉄骨造の2種類がある。
てっこつラーメンこうほう【鉄骨ラーメン工法】
柱、梁を重量鉄骨で構成し、その接合部が固定されている工法。材と材が交わる部分が剛接合によって固定されているのが特徴。耐震性や耐久性が高く、集合住宅など中高層の建物に採用されることも多い。
どうせん【動線】
人の移動を示した線。間取りなどを考える際に、家族の動線に配慮すると使いやすい家にすることができる。
としけいかくほう【都市計画法】
計画的な都市づくりを進めるための基本的な法律。適正な制限のもとに、土地の合理的利用が図られることを基本理念とする。全国の土地は都市計画区域外と都市計画区域内に分けられていて、このうち、都市計画区域内は、市街化調整区域、市街化区域、及びその区域がまだ決められていない未線引き区域に分かれている。
どだい【土台】
建物の脚部(最下部)に位置する部材(木材)のこと。柱からの荷重を基礎に伝える役割をもつ。
トップライト
屋根面にとった採光用の窓。天窓。周囲に建物が立て込んでいる場合などに有効。
な行
ないそうざい【内装材】
床、壁、天井などに使う材料の総称。室内に直接面したフローリング、カーペット、タイル、壁クロス、合板、塗装材などの仕上げ材のほか、そのすぐ下の下地材を含めていうことが多い。
ぬのきそ【布基礎】
建物の外周および内部の必要な部位を囲むように巡らされた基礎。一般住宅の基礎はほとんどがこの方式だが、断面の寸法や鉄筋のサイズによって構造耐力が異なるので、注意を要する。
のべゆかめんせき【延床面積】
地階、1階、2階など、各階の床面積の合計。バス、トイレ、収納スペースなども含む。小屋裏の物置やデッキは含まない。
は行
パース
建物の外観や室内の空間のイメージがわかりやすいように、立体的に描いた透視図。
パイプスペース
給水や排水、ガスなどの配管スペース。平面図や設備図では「PS」の略号で記載されている。
パッシブソーラー
太陽光発電や太陽熱温水器のような装置を使って太陽エネルギーを取り入れるのではなく、設計の工夫で太陽エネルギーを蓄熱材などにたくわえ利用すること。これと対照の方式が「アクティブソーラー」。
はり【梁】
屋根を支える構造材で、柱の上に渡す。木造の場合は、2階の床を支える「床梁」と、小屋組を支える「小屋梁」がある。
ふどうちんか【不同沈下】
地盤が悪く、建物が不揃いに沈下を起こすことをいう。家全体が均等に沈下するのではなく、一方向に斜めに傾くような状態となる。
フラット35
民間金融機関による長期固定金利の住宅ローン。この債権を住宅金融支援機構が買い取り、証券化して投資家に販売するしくみとなっている。
プレカット
あらかじめ部材を施工現場で使用する寸法にカットしておくこと。施工現場での作業の簡略化を可能にし、施工期間の短縮や労働力の削減をはかることができる。
プレハブこうほう【プレハブ工法】
あらかじめ工場で生産された屋根や壁、床などの部材を現場に運んで組み立て建築していく工法。一定の基準をクリアしたプレハブ住宅には「優良工業化住宅」の認定が与えられ、一定の品質が保証されている。
へいめんず【平面図】
いわゆる間取り図。真上から見下ろしたように表現されている。開口部の種類などもわかるように描かれている。
ベタきそ【ベタ基礎】
建物の下部を全部基礎にすること。特に地盤の悪い場合に用いられる。基礎が一体化しているので不同沈下しにくい。
ま行
メーターモジュール
住宅のモジュール(設計基準単位)を1m間隔で設定したもの。木造住宅で多く用いられている尺モジュール(91 )に比べ、住空間が約20%アップする。
もくぞうじくぐみこうほう【木造軸組工法】
「在来工法」のこと。
もりつち 【盛土】
斜面地などを造成する際に、土を盛って平らな敷地を作ること。
や行
ユーティリティ
洗濯・アイロンがけなどの家事作業を行うための諸設備を設けたスペース。洗濯からアイロンがけなど一連の作業や縫い物、ちょっとした書き物が一カ所でできるようにしていることも多い。物干しスペースなどを設けたものもある。
ユニットバス
壁、床、天井、浴槽を一体化して工場で生産された浴室。最近ではシステムバスとも呼ばれる。
ようじょう【養生】
工事中に建物が傷んだり汚れたりしないように、また近隣に塗料や工事で発生するゴミが飛散しないように、シートや覆いを掛けて保護すること。コンクリートの打設のあと、強度が出るまでの間、湿潤に保ち、水分が失われないように、覆ったり散水したりすることも養生という。
ようせきりつ【容積率】
敷地面積に対する建物の延床面積の割合のこと。都市計画区域内においては建築基準法の規制により、用途地域の種別や前面道路の幅員等により容積率の上限が定められている。
ら行
ライトコート
中庭のひとつ。光庭ともいう。建物の中心部に採光や風通しのために設けた吹き抜けスペース。ライトコートに面する窓を設けることで、室内に光が取り入れられる。
りつめんず【立面図】
建物の外観を表した図。投影画法で、立画面に投影する。東西南北それぞれの面を描き、縮尺を平面図と同一にするのが原則。
ロフト
屋根裏部屋。最近では屋根裏でなくても、部屋の中ほどの高さにつくられたスペースのこともロフトと呼ぶことが多い。


